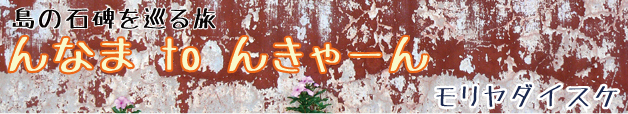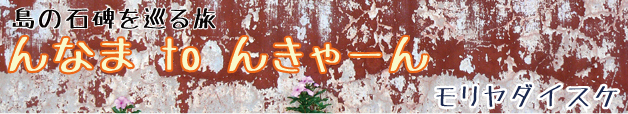
連載200回突破記念特番、三部作の2本目です。今回、お届けするのは加那浜矼道と呼ばれる矼道(橋道)。こちら、出落ち感のままに書いてしまうと、別名を「下地矼道」と呼ばれる与那覇湾の最深部に作られた海中道路の名前です。
与那覇湾の奥で矼(橋)といったら、やはり崎田川に架かる「池田矼」がまず頭に浮かぶのではないでしょうか?。加那浜矼道に進む前に、まずは池田矼から攻めてみたいと思います。たぶん、これだけでも一本のネタになるレベルなんですけど、今回はお祝いの特番ですから~!

石田矼は正徳年間(1506~21年)に仲宗根豊見親の命により、平良と下地を結ぶ街道にあった湿地帯の通行困難を解消するために構築されたと云われています。
「雍正旧記」(1727年)によると、「池田矼、南北長20間、横3間、高サ9尺5寸村北ノ潟陸原ニアリ」と書かれており、すでに石矼が存在していことを示しています。また、後の1817(嘉慶22)年にはなんらかの理由により、大改修が施されたことが「宮古在番記」にも記されています。



この矼の架橋時の伝承として、工事宰領の役人が病に罹ったり、死亡するなど不吉なことが多く、水神の怒りを鎮めようと、巨牛一頭を贄にしてようやく完成したといわれています。そんな池田矼ですが、石積みの美麗さや年代の古さなどが見どころとして取り上げられていますが、ここではひと味もふた味も違うとこから切り込んでおきましょう。
まず、訴えたいのはこの矼の名前です。沖縄県指定の史跡に1977(昭和52)年に指定されているのですが、その指定名、つまり史跡の本名ともいうべき呼称は、「下地町の池田矼」というのです(宮古島市文化財要覧 2011)。もちろん、この下地町は「沖縄県宮古郡下地町」のこと。2005(平成17)年に5市町村合併で宮古島市になった今も、その名は変更されることなく残っているのです(宮古関連でこのような例は、城辺町の友利のあま井かあります。ただ、こちらはあま井を名乗る井戸が複数あることも影響していると考えられます)。


 【左:池田矼天面。clickで線路イメージ表示】【中:レールの柵支柱】【右:錆びたレール。clickでレール位置表示】
【下:軌道敷のような小径】
【左:池田矼天面。clickで線路イメージ表示】【中:レールの柵支柱】【右:錆びたレール。clickでレール位置表示】
【下:軌道敷のような小径】

続いてもうひとつ。
この池田矼、確かに琉球石灰岩の切り石を組み上げた素晴らしい石橋であるには違いないのですが、矼に近づいでよーく見ると、矼の一番上、天面はコンクリートで固められているのです。県の史跡ですが、これってアリなんでしょうか。
実は、指定年月日を考えたら、あながちアリなのです。というのも、この現場をよーく見てください。矼の向こう側は製糖工場の敷地になっており、崩れかけた柵があります。その柵の支柱がなんと細身のレールなのです。
さらにもっとよく観察してみると、製糖工場側の土盛りの中から錆びた鉄材が2本、中空に突き出しています。その幅目算で70センチくらい。そう、これは明らかにレールです。おそらく軌道幅は幅762ミリ。いわゆる特殊狭軌、ナロ―ゲージと呼ばれる軌道と思われます。
しかも、矼のサイズから見ると複線分の幅があります。天面のコンクリートに積もる落ち葉などを履きだして、路面をチェックすると、複線の軌道と枕木の痕のようなものがふた筋ほと見えてきました。さらに、矼への取りつき道路は緩く左にカーブしており、まるで廃線跡のようです。
 【池田矼の上流に架かるコンクリート橋】
【池田矼の上流に架かるコンクリート橋】
間違いなくこれは戦前、大正時代に製糖工場へキビを運搬するため、島内に張り巡らされたトロッコ軌道の痕跡に違いありません。その距離は約43キロにも達していたといいます。けれど、当時の資料は果てしなく少なく、判らないことだらけなのてすが、虫食いでルートの解明など地味に聞き込みや史料収集をして解明を目指しているのですが、1945(昭和20)年の空中写真では、工場南部にヤードが存在し、南側から場外へレールが続いているように見えます。もちろん工場北側の池田矼は存在していますが、そこに道らしきものはありません。あるのはその少し上流に作られた、もう一本の橋が工場北側のへのメインルートになっているように見えます。
こちらの橋はコンクリート橋で、今も現存していますが、道としてはすでに廃道となり、橋だけが遺構として残っている状態です。ところがこちらの橋の部分には、未だにレールが残っているのです(空中写真では軌道の有無は確認できない)。しかし、それ以外は激しいジャングルで、痕跡も怪しいのです(残念ながら、まだ工場の敷地内は未調査)。


 【左:コンクリート橋の天面】【中:レールが隠れています】【右:下流の池田矼をのぞむ】
【左:コンクリート橋の天面】【中:レールが隠れています】【右:下流の池田矼をのぞむ】
ちなみに、1944(昭和19)年10月10日の十十空襲以後、繰り返し行われた空襲で平良の町などは焼け野原のようになっていたのに、不思議なことに1945(昭和20)年に撮影された空中写真で、これだけ大きな工場なのに爆撃を受けていません(騎機銃掃射はあった)。
話がちょっと脱線し始めているので、転覆しないうちにこのあたりで止めておきますが、この“シュカートレイン”のネタは、大げさにいえばライフワークとして追いかけている自由研究なので、いずれまた報告出来る機会もあるかと。
余滴として、製糖工場の話(宮古製糖なのにトレードマークが丸にTの理由とか)は、
第56回「竹野寛才氏之像」の回で語っています。

 【左:加那浜矼道の起点?。赤名宮の裏から西を眺望】【右:加那浜橋道の終点?。池原半島東部】
【左:加那浜矼道の起点?。赤名宮の裏から西を眺望】【右:加那浜橋道の終点?。池原半島東部】
さて、話を矼道に戻します。
ここまでつらつらと書いて来ました池田矼と、タイトルの加那浜橋道(下地矼道)は、同じ時期に作られたと云われています。崎田川に橋を架けた池田矼と違い、加那浜と呼ばれた与那覇湾の最深部の沿岸部に海中道路を築いたのが加那浜橋道です。
前述しましたが、正徳年間(1506~21年)に仲宗根豊見親の命によって、平良と下地を結ぶ街道にあった湿地帯を安全に通行するために構築されたと云われています。小さいとはいえ崎田川の河口付近に湿地帯がありそうなことは、どことなく簡単に想像することが出来ますが、池田矼から上地の池原半島まで綺麗な円弧を描いた海岸線に、湿地帯などあるのかと思ってしまいます。前回の
佐和田矼道は砂洲が広がる砂地でしたが、この加那浜が面している与那覇湾は泥の海なのです。つまり、干潮になって姿を現す海底は海水をたっぶりと含んだ泥。つまり湿地帯なのです。
当時の状況を知る手がかりが、
「宮古史伝」に収録されいる『下地橋積上げのアヤゴ』の歌詞から見てとることができます。
下地女童(めやらび)や 田の上女童や うきみざうの かな浜の道から
訳:下地乙女は、田の上の乙女は、うきみざうの、かな浜の道を(往くに)から
七ばた合(ちあ) いちや足らい下裳(かかむ)や 腿根がめ たもとがめからげ
役:七幅合せた、晴着の下裳を ふと腿まて、袖下までからげて
平良道 おやむそね通ひ居る 其(う)れ見たり 目と見たり痛(いちや)さぬ
訳:平良道を、上方へ通うて居り それを、目のあたり見れば、見苦しくて
下地みな 田ぬ上みな 集ひ 男等(びきりや)すや石持ち、女等(ぶなりや)すや土(んた)持ち
訳:下地(の者)みな、田の上(の者)みな、集めて 男等は石を運び、女等は土を持ち運び
橋積み上げ 石積みあげからや 七ばた合 あたるヒダ下裳ばた 踵(あど)たらす 地払ふて通ひ居て
訳:橋を積み上げ、石を積み上げて、道を開けて後は 七巾合わせた下裳も踵まで地面まで垂らして通う居る
着物の裾を太腿が見えるほど捲って街道を歩いて平良を往来する姿ははしたないと詠われ、住民総出で石を積んで矼道を作り上げてからは、裾を捲ることなく通ることができるようになった、という感じでしょうか。
 【「宮古の史跡・文化財」宮国定徳(1975年)より、下地橋道の紹介。どこを撮影しているのかは不明】
【「宮古の史跡・文化財」宮国定徳(1975年)より、下地橋道の紹介。どこを撮影しているのかは不明】
加那浜矼道は南北(の長さ)5町46間、横(の幅)1間2尺、高さ6尺と「雍正旧記」に記されており、宮古郷土史研究会「新版 宮古の歴史を訪ねて(1999)」では、判りやすく長さ623メートル、幅2.4メートル、高さ1.8メートルとをサイズを算出しています。
「沖縄県歴史の道調査報告書Ⅷ 宮古諸島の道」によると、「崎田川まで道は崎田橋、池田矼となって矼をこえ、与那覇湾奥の加那浜に入る(中略)、「下地橋道」別名加那浜橋道につながる。橋道を上った場所が上地のウクミザー、上地村番所のすぐ北隣である」とルートが記されていた。ウクミザーの正確な位置が不明なのですが、上地番所は旧下地町役場であった宮古島市下地保健福祉センター(と隣に新しく移転した下地郵便局)にあたります。また、この郵便局の道向かいにはヤマトゥ御獄が鎮座しており、その背後は護岸された与那覇湾になっていることから、位置関係を考えるとこの辺りが加那浜矼道の上陸地点になるのではないかと考察できます。ところが、前述の郷土史研の623メートルでは池田矼から届かないのです(崎田橋は現在の国道に架かる橋と同名)。
 【「下地地区の史跡を歩く」(第5回宮古島市総合文化祭 2010年史跡巡りの栞から。イラスト:砂川明増】
【「下地地区の史跡を歩く」(第5回宮古島市総合文化祭 2010年史跡巡りの栞から。イラスト:砂川明増】
ひとつ気が付いて疑問に感じたことがありました。郷土史研が算出した尺貫法の換算は、現代の日本で利用されている、33分の10メートル(1尺≒0.303メートル)を基準にして算出されている点です(5町46間=2076尺≒629.09メートルとなるのだけれで、なぜか郷土史研の数値は少し短い)。
当時の琉球は大陸の影響を強く受けている訳ですし、モノをやり取りするには同じ尺度が必要なことを考えると、大陸の度量衡(この場合、尺貫法の貫は日本独自の単位なので、読み替えとしては度量衡としてみた)は、清の時代だと、裁衣尺:1尺=35.5センチ、量地尺:1尺=34.5センチ、営造尺:1尺=32.1センチと、用途に応じた3つの尺位がありました(日本にも鯨尺という尺位があり、特に布もの系はこちらを使っており、近代琉球あたりでは織物の単位として使われていた模様)。
実際、どれが使われていたかは、未明状態なのですが、これを元に加那浜矼道の長さを換算してみると、もっとも長い裁衣尺で737メートル、もっとも短い(といっても日本の尺=曲尺よりも長い)造営尺でも666.4メートルになります。


 【左:国土地理院地形図。ほぼ現行の土地利用状況】【中:米軍制作の地図(1945年)。建物の数やため池がなく、地形的変化もある】【右:米軍撮影の空中写真(1945年)。製糖工場にトロッコヤードが確認できます】
【左:国土地理院地形図。ほぼ現行の土地利用状況】【中:米軍制作の地図(1945年)。建物の数やため池がなく、地形的変化もある】【右:米軍撮影の空中写真(1945年)。製糖工場にトロッコヤードが確認できます】


 【左:国土地理院空中写真(1962)。製糖工場が大きく変化しています】【中:国土地理院空中写真(1977)。下地町内の各地で開発が始まりした】【右:国土地理院空中写真(1995)。池原地区が埋め立てられています】
【左:国土地理院空中写真(1962)。製糖工場が大きく変化しています】【中:国土地理院空中写真(1977)。下地町内の各地で開発が始まりした】【右:国土地理院空中写真(1995)。池原地区が埋め立てられています】
矼の長さとしては700メートルを越えれば、どうにか届く距離になりますので、きっとこの尺位であったのではないかと愚考しました。ただ、もうひとつ気がかりな点がありまして、実は郵便局の北側に崎田川とは別の小さな川があるのです。水量は多くはありませんが枯れることなく流れています。無名の小水路なのであまり問題視はされてはいませんが、この流れは下地小付近から続いており、かつてこの流域には田圃もあったようです(根源的な水源は、宮星山やイリノソコといった丘陵地を背後に持つ、嘉手苅の南方は多数の湧水域になっており、宮古で1・2を争うほど低い分水嶺を改修する、治水が古くからおこなわれている)。

 【左:名もなき川の河口。矼道はどこにあったのでしょう】【右:名もなき川。郵便局脇の国道の下を潜っています】
【左:名もなき川の河口。矼道はどこにあったのでしょう】【右:名もなき川。郵便局脇の国道の下を潜っています】
この川の北側に加那浜矼道が接しているとしたら、この川を越える橋が必要になります(矼道で河口を塞ぐのは理にかなわない)。ましてや村番所の隣に着くのですから、立地としても申し分ない位置関係です。けれど、こちらの橋については一切の記録がありません。まさに、無名の川の無名の橋として歴史の中に埋もれているのです。
この番所前で道は左右に分れ、右へ行くと与那覇の集落へ。左へ行くと、洲鎌、嘉手苅を経て、入江から宮国、新里と東進し、砂川、友利、そして保良へ続く、平良からの親道(当時の国道)となっています。これはルートこそ大きく変化していますが、今も日本最南端・最西端の国道390号線として受け継がれています。



 【上:現在の綺麗に補修された製糖桟橋】【左:2013年2月頃の製糖桟橋】【中:下まで綺麗に石積みがされています】【右:桟橋に残っていた孔痕と製糖工場】
【上:現在の綺麗に補修された製糖桟橋】【左:2013年2月頃の製糖桟橋】【中:下まで綺麗に石積みがされています】【右:桟橋に残っていた孔痕と製糖工場】
この与那覇湾の最深部となる上地(一部、与那覇)。西側の池原は埋め立てられて、新しい下地町の庁舎が建てられるなど近年になって大きく変化しましたが、加那浜は親道から国道となり車の世になっても、幾度かの護岸改修はされましたが、大きく変化はしていません。そんな中にひとつ、ニョキっと海に突き出している、気になるものがずっとあったのではないでしょうか。これについて最後に触れておきます。
この出っ張りは石組みの埠頭なのです。道路を挟んだ反対側にある、製糖工場へキビを搬入したり、黒糖を搬出するために作られた製糖桟橋と呼ばれています。どのように使われていたかがはっきりしないのですが、島内にトロッコを張り巡らせるくらいでしたので、大量に船に積み込んで工場から搬出していたとしてもおかしくありません(現在のマティダ劇場あたりが、島から出荷する黒糖を集積し、船に積み込んでいた第二埠頭でした。今も、マティダ劇場の前には宮糖の倉庫があります)。

 【左:国道の崎田橋から与那覇湾をのぞむ】【右:沖に見えている謎の遺構。clickで矢印表示】
【左:国道の崎田橋から与那覇湾をのぞむ】【右:沖に見えている謎の遺構。clickで矢印表示】

 【左:直線的に続く謎の遺構】【右:満潮時は海中に没してしまう、沖合の遺構】
【左:直線的に続く謎の遺構】【右:満潮時は海中に没してしまう、沖合の遺構】
加那浜の製糖桟橋は護岸工事たびに短くなってしまい、今ではその長さも半分ほど。以前は埠頭に据えられていた重機(クレーン的なもの)の施設痕もあったのですが、いつのまにか綺麗に石を組み直してしまい、近代遺構が消失してしまいました(もっとも大穴があいていたので、安全性を考慮した結果と思いますが残念です)。現在もここは特に説明がないので、これがなんなんのか知らない人も多いかと思います。
知らないついでにあげておくと、崎田橋(国道に架かる橋)の下あたりから、与那覇湾の中央に向かって、四角いコンクリートの遺構が点々と海の中にあるのをお気づきでしょうか?。
全貌は大干潮にならないと沖合の方は姿を現さないのですが、形状からして桟橋の土台と思われます。それも橋梁のような桁のある作りのようなタイプだと考えられます。もしかするとこれは、沖合の船に黒糖を速やかに大量に積み込むための、トロッコ桟橋だったのではないかという、夢のような妄想が浮かぶのでした(空中写真でも川満漁港から奥に船は行きそうにないのに、少し浚渫されたような場所が見える)。
そうすれば工場の北側に軌道が伸びていたことも、ちょっとは説明がつきますし、与那覇湾は干満に大きく左右されるため、小さな舟しか接岸できない製糖桟橋よりも有効な施設と考えられます。ところが、こちらもまったく資料がなく、いつ頃のモノなか、実際はどういった施設だったのか、などなにひとつ判らないのです。
日々、クリームソーダ色の与那覇湾を眺めては、ついつい妄想ばかりが膨らんでしまうのでした。誰かこの謎をズバッと解決してくれませんか?。